こんにちは!
しらたまです。
しらたまとは?
30代の糖尿病内科医です。
普段は3歳のちびたま(息子)を育てながら臨床医として働いています。
私は同年度に
第34回糖尿病専門医試験
第2回糖尿病代謝内分泌領域専門医試験
のダブル受験をし、
無事両方とも合格する事ができました。
実際に試験を受験したしらたまが試験対策として大切だと思うキーワードにマーカーを引いています。
※本記事は参考文献を元に個人的に記載したものです。利用時は自己責任で必ず参考文献も確認して下さい。
※病態に関するご質問にはお返事しておりませんのでご了承下さい。
※誤った記載があった場合には内容確認後に修正するので、ご連絡下さい。
参考文献
 | 内分泌代謝・糖尿病 内科領域専門医研修ガイドブック [ 日本内分泌学会 ] 価格:9240円 |
↑これをメインの教科書として使用しています。
↓この2冊を解いて重要そうなキーワードを盛り込んでいます。
 | 内分泌専門医に絶対合格したい人のための問題集 第2版【電子版付】 [ 井林雄太 ] 価格:7480円 |
 | 内分泌代謝・糖尿病専門医のセルフスタディ230 [ 田辺 晶代 ] 価格:5280円 |
↑今までウェブ版しか購入できなかったセルフスタディが2025年6月に刷新して発売されていました!!私は古い版を使って受験しましたが、ガイドラインの改訂にも対応しているようなので、受験する方は取り組むことをおすすめします!!
原発性副甲状腺機能亢進症(PHPT)
病態
腺腫が80%以上で一番多い。
過形成は15%程度(MENを疑う)
CaSR(Ca感知受容体)の細胞表面における発現低下により発症
高Ca血症が起きる機序:PTHが
・骨吸収促進作用(破骨細胞の形成や機能を亢進させる)
・腎臓の遠位尿細管からのCa再吸収促進
・腎臓の近位尿細管での活性化VitD(=1,25(OH)2D)の合成促進
・→腸管からのCa吸収増加
高Ca血症になり、Caの糸球体濾過量が増加し、PTHのCa吸収量を上回る
→高Ca尿症になる
低P血症が起きる機序:PTHが
・腎臓の近位尿細管でのP吸収を抑制する
PTHが尿細管でのHCO3–の再吸収を抑制しCl–を再吸収する
→高クロール性代謝性アシドーシスをきたす
疫学
中高年の女性に多い
主要症候
Ca11-12mg/dLになると
・多尿・口渇(腎での尿濃縮力の低下に伴う)
※多尿はAVP作用の減弱によっても生じる
・近位筋力の低下(神経・筋障害)
・悪心・便秘(消化管運動の低下)
・集中力低下・うつ症状
・消化性潰瘍・膵炎(ガストリン分泌亢進による)
・骨折リスクが上昇
・尿路結石・腎石灰化(高Ca尿症による)
尿濃縮力の低下による脱水や腎臓へのCa負荷による急性腎障害を起こす
→Caがさらに上昇する悪循環に→高Ca血症クリーゼに。
無症候性PHPT:
・高Ca血症による自覚症状がない
・椎体骨折や尿路結石の存在を自覚していない
検査
血液検査
・CaとPTHを相対的に評価する
・P:正常低値〜低値
・1,25(OH)2Dは正常高値〜高値
・25(OH)Dは低値 →骨塩量は低下する。
・尿中Ca:女性は250mg/日以上、男性は300mg/日以上で高Ca尿症と判断
・%TRP(尿細管P再吸収率)低値
・骨形成マーカー、骨吸収マーカーともに上昇
骨密度測定
・皮質骨優位の骨量減少
→橈骨遠位1/3や大腿骨頸部骨密度の低下を認める
※閉経後などPHPT以外の要因でも骨密度は低下するため、一様ではない
腹部エコー、腹部CT
・尿路結石、腎石灰化の有無を評価
局在診断
・カラードプラを用いたエコー
・テクネシウムシンチ(99mTc-MIBI) など
5-10%に胸腔内などの異所性の副甲状腺が存在する場合があり、その場合は99mTc-MIBIやSPECTによる三次元解析が有用。
局在診断で複数腺の腫大が見られる場合には必ずMENの合併を疑って精査を行う。
診断
高Ca血症にも関わらずPTHが高値の場合に疑う。
リチウム製剤や家族性低Ca尿性低Ca血症が否定できたらPHPTと診断できる。
サイアザイド系利尿薬も尿中Ca排泄を減少させる。
治療
根治治療は病的副甲状腺の摘出。
「すべての症候性PHPTは手術療法に問題となる合併症がなければ手術療法を選択すべき」
無症候性の場合は、下記の表でひとつでも認める場合は手術適応となる。
| 血中Ca濃度 | 正常上限より1.0mg/dLを超える上昇 |
| 骨 | X線検査による椎体骨折の存在 骨密度Tスコア-2.5SD以下 (測定部位(腰椎,大腿骨頸部,前腕)は問わない) |
| 腎 | eGFRまたはCcr60ml/分未満 腎石灰化,尿路結石の存在 (X線,エコー,その他の画像検査) 尿中Ca排泄量 (女性>250mg/日、男性>300mg/日) |
| 年齢 | 50歳未満 |
これらの項目が満たされていない場合でも、患者の同意が得られて手術の禁忌がない場合には手術を選択できる。 ※P値は基準にない!!
手術療法
単線腫大の腺腫は腺腫のみ摘出。
過形成の場合は全腺摘出後に一部を自家移植する。
癌は拡大頸部手術。
術前からビタミンDの補充や骨代謝回転が顕著な場合には術前からビスホスホネートを投与する
→ハングリーボーンによる低Ca血症をきたしにくくする。
内科的治療
手術困難例や再発例には高Ca血症と骨粗鬆症に対して治療を行う。
正常上限の1mg/dL以上のCa値の上昇に対して
シナカルセト(=レグパラ)、エボカルセト(=オルケディア)が適応(CaSR作動薬)。
→Ca値の持続的な低下効果はあるものの、PTHはわずかに低下させるだけで正常化には至らない。なので骨密度増加効果はない。
骨粗鬆症の治療薬としてビスホスホネート(主にアレンドロン酸)の骨密度増加効果が報告。
デノスマブも有用の声がある。
→いずれも持続したCaの低下効果はない。骨折防止効果も示されていない。
デノスマブは中止後速やかに骨吸収が亢進するため、中止の際には必ずビスホスホネートなどで逐次治療が必須。
ビタミンD不足や欠乏はPHPTの重症化に関わる。
天然型VitDの補充は血中や尿中のCa値の優位な上昇をきたす事なくPTHを抑制する。
25(OH)D<30ng/mLの場合は天然型のVitD(Ca非含有のもの)の補充が推奨。
予後
腺腫の場合は摘出術で予後は良好。
過形成や癌は再発例がしばしばある。
無症候性例はアメリカでは65%は手術なしでも病態は増悪しなかった。
無症候性の場合でも37%は症候の進行や骨密度の低下をきたしていた。
→PHPT非手術例では
年に1回のCa、PTH、eGFR(orCcr) 、25(OH)Dの測定と
1-2年毎に骨密度測定、椎体骨折判定、尿路結石の確認がガイドラインで推奨。
経過観察中に手術適応の表の項目に合致や脆弱性骨折を認めた場合は手術適応。
終わりに
カルシウムリン代謝に苦手意識を持っている先生も多いのではないでしょうか?
キーワードを抑えると問題が解きやすくなると思います。
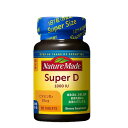 | NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパービタミンD(1000I.U.) 90粒 90日分 価格:1104円 |
天然型のビタミンD製剤が処方できる世界線は来るのでしょうか?
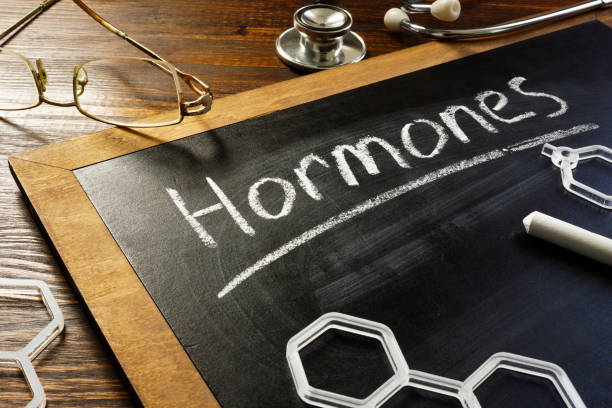


コメント