こんにちは!
しらたまです。
しらたまとは?
30代の糖尿病内科医です。
普段は3歳のちびたま(息子)を育てながら臨床医として働いています。
私は同年度に
第34回糖尿病専門医試験
第2回糖尿病代謝内分泌領域専門医試験
のダブル受験をし、
無事両方とも合格する事ができました。
糖尿病専門医試験の勉強をする中で、一番の難関だったのが、「記述対策」でした。
勉強始めは記述がうまく書けなかったり、想定問題を自分で作るのも難しかったりと壁によくぶつかっていました。
専門医に合格した立場から、今後試験を受けるなら事前に対策しておくなと思う範囲の想定問題と知識のまとめをお伝えします。
※本記事は参考文献を元に個人的に記載したものです。利用時は自己責任で必ず参考文献も確認して下さい。
※誤った記載があった場合には内容確認後に修正するので、ご連絡下さい。
ひとこと
緩徐進行型1型糖尿病の診断基準は選択で出題される可能性もあるので、マストで暗記しておく必要があります。
probableの内服薬の選択に関しては、まだ保険診療の適応病名が追いついていませんが、記述で出題される可能性は十分あるかなと思います。
想定問題
緩徐進行型1型糖尿病について下記の問いに答えよ
1.下記の文章の(ア)〜(キ)の穴埋めをせよ
緩徐進行型1型糖尿病の診断基準(2023)は、1.経過のどこかで(ア)が陽性である。2.原則として糖尿病の診断時(イ)もしくは(ウ)はなく、ただちには高血糖是正のためのインスリン療法が必要にならない。3.経過とともにインスリン分泌が緩徐に低下し、糖尿病の診断後(エ)を過ぎてからインスリン療法が必要になり,最終観察時点で内因性インスリン分泌は欠乏状態(空腹時血清Cペプチド<(オ))である。上記1,2,3を満たす場合は、(カ)と診断する。上記1,2のみを満たす場合は、インスリン非依存状態の糖尿病であり、(キ)とする。
2.(キ)への適切な治療介入に関して述べよ(300字)
模範解答
1.(ア)膵島関連自己抗体(イ)ケトーシス(ウ)ケトアシドーシス(エ)3ヶ月(オ)0.6ng/mL(カ)緩徐進行型1型糖尿病(difinite)(キ)緩徐進行型1型糖尿病(probable)
2.緩徐進行型1型糖尿病(probable)はインスリン非依存状態である事から、必ずしも早期のインスリン療法が必須とはならない。メトホルミンやDPP4阻害薬の使用は内因性インスリン分泌が保持される可能性が示唆されており使用を検討する。SU薬は早期に内因性インスリン分泌を低下させる可能性があるため、使用は推奨されない。GLP-1受容体作動薬はHbA1c低下の報告はあるものの、エビデンスが限定的であるため注意する。いずれの薬剤を選択した場合でも定期的な血糖コントロール状態の把握や内因性インスリン分泌を評価し、内因性インスリン分泌の低下が疑われた場合には速やかにインスリン治療を導入するなどの治療変更が必要である。(293文字(英語と数字は2文字で1字カウント))
内容の要約
0.緩徐進行型1型糖尿病の診断基準(2023)
1.経過のどこかの時点で膵島関連自己抗体が陽性であるa)
2.原則として、糖尿病の診断時、ケトーシスもしくはケトアシドーシスはなく、ただちには高血糖是正のためのインスリン療法が必要にならない
3.経過とともにインスリン分泌が緩徐に低下し、糖尿病の診断後3ヶ月b)を過ぎてからインスリン療法が必要になり,最終観察時点で内因性インスリンは欠乏状態(空腹時血清Cペプチド<0.6ng/mL)である
判定:上記1,2,3を満たす場合は、「緩徐進行型1型糖尿病(difinite)」と診断する。上記1,2のみを満たす場合は、インスリン非依存状態の糖尿病であり、「緩徐進行型1型糖尿病(probable)」とする
a)膵島自己抗体とはGAD抗体,ICA,IA-2抗体,ZnT8抗体,IAA(インスリン自己抗体)を指す。ただしIAAはインスリン治療開始前に測定した場合に限る
b)定型例は6ヶ月以上である
1.インスリン依存状態へのリスク評価
・抗GAD抗体≧10U/mLの高力価
→2015年までのGAD抗体RIA法では≧10U/mLの高力価の場合には、その後のインスリン依存状態への進行リスクが高いと言われていたが、ELISA法では依存状態への進行リスクについて結論が出ていない。
・複数の膵島関連自己抗体が陽性の場合は進行リスク高い。
・Ehime StudyではTPO抗体陽性の場合はインスリン依存状態へ進行するリスクが高いと示されている。
・BMI低い、発症年齢若い、糖尿病診断からGAD抗体陽性の確認までの期間短い、診断時のCペプチド低いも依存状態への進行のリスク因子
2.薬剤選択
推奨:DPP4阻害薬,メトホルミン
エビデンスが限定的:GLP-1受容体作動薬
非推奨:SU剤
推奨しない:チアゾリジン
見解なし:SGLT2阻害薬,α-GI,グリニド,イメグリミン
・difinite診断例はインスリン加療を行う
・probableはインスリン加療も望ましい治療ではあるが、全例早期使用のエビデンスはない
・SU薬の使用は内因性インスリン分泌能の低下を進めるため推奨しない
→SU薬が膵島β細胞における抗原提示を促進して、免疫担当細胞による破壊を進めてしまう可能性が示唆されている
・GLP-1はHbA1c改善効果の報告はあるが、エビデンスが少ない
3.治療後の経過観察
・経時的に血糖コントロール状態と膵島β細胞機能(Cペプチド)を評価する
・血糖コントロールの悪化や内因性低下を疑った場合は速やかにインスリン加療を開始
終わりに
参考文献の本文中に治療方針のアルゴリズムが図解で乗っているので、ぜひご参照ください。

 | ゴディバ公式(GODIVA) ハート オブ ゴールド コレクション(6粒入) 価格:2160円 |
「1型糖尿病」の診断を受けて、ショックを受けられる患者さんは多いです。必要な知識を身につけて適切な治療介入をすれば、出来ないことは何もないし、食べられないものも何もないと伝える様にしています。
参考文献
糖尿病66(12):807-814,2023
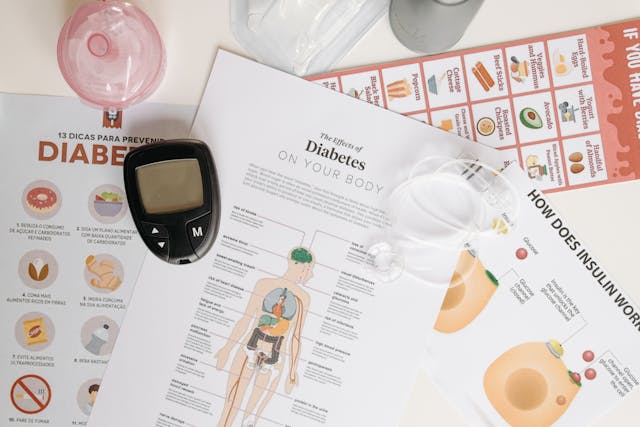


コメント