こんにちは!
しらたまです。
しらたまとは?
30代の糖尿病内科医です。
普段は3歳のちびたま(息子)を育てながら臨床医として働いています。
私は同年度に
第34回糖尿病専門医試験
第2回糖尿病代謝内分泌領域専門医試験
のダブル受験をし、
無事両方とも合格する事ができました。
糖尿病を専門に日々診療していると、「肥満症」の定義に当てはまっていなくとも、GLP-1受容体作動薬、GLP-1/GIP受容体作動薬を使う機会は多く、改めて「肥満症」か否かを判断する機会は意外と少ないなと感じています。
だからこそ「ウゴービ」、「ゼップバウンド」の適応に当てはまる人か否かを判断して治療介入していくのは必要な知識ですし、昨今美容業界に不適切な使用が目立っているからこそ、しっかりと疾患に向き合わなければいけない領域です。
需要が高いからこそ、選択問題、記述問題共に試験で問われる可能性が高い分野だと思っています。
今回は「肥満症」を中心に想定問題とステートメントの概要をお伝えして行きます。
※本記事は参考文献を元に個人的に記載したものです。利用時は自己責任で必ず参考文献も確認して下さい。
※病態に関するご質問にはお返事しておりませんのでご了承下さい。
※誤った記載があった場合には内容確認後に修正するので、ご連絡下さい。
その前に経験談
個人情報なので詳しいことは記載できませんが、外来で脂質異常症の加療で通院している患者さんで肥満にすごく悩んでいる女性がいました。
二次性肥満のスクリーニングも行いましたが、陰性でした。
「痩せたいのに痩せられない。どうすればいいか分からない。。このままだとどんどん不健康になっていく気がする。。」
暗い顔で診察室でお話しされています。
BMIは30ないくらい。糖尿病はありません。
糖尿病の診断がついていれば、マンジャロのいい適応なんだけどな、、、
こちらも歯がゆい気持ちです。
そんな時に肥満症治療薬のことを思い出します。
脂質異常症の診断はついているから、もう1つ健康障害が見つかれば治療介入できる!
脂肪肝も以前から指摘されていたので、GLP-1受容体作動薬の適応があるかもしれないとお話ししました。
私が働いている職場では導入の施設基準を満たしていないので、他院に紹介することになります。
紹介する時に患者さんに伝えておくことで大切なことは、
紹介先ですぐに薬物加療がスタートする訳ではない
少なくとも半年は食事療法が必須であり、そのための定期通院も必要である
薬だけの力で痩せるのではなく、本人の生活週間の改善はずっと必要になる
これらを紹介前に伝えておくだけで、患者さんの意識は大分違うと思います。
その方は紹介先に受診後も、肥満症とは関係ない併存疾患で私の外来を定期的に通院されています。
その後診察室でお会いしたとき
「紹介して頂いてありがとうございました。今は定期的に栄養指導を受けながら食事を頑張っています。」
と明るい顔でお話ししてくださいました。
治療介入できる施設はかなり限られているので、施設基準を満たさない職場で働いている先生の方が多いと思います。
ただ、適応を見極めて適切に紹介することがとても大切である事をこの患者さんで学びました。
こんなに感謝される職業っていいなって☺️
嬉しくなった思い出でした☺️
想定問題
選択問題
肥満症の診断基準に含まれている健康障害の中で誤っているものは何か?1つ選べ。
A.冠動脈疾患
B.脳梗塞
C.月経異常
D.アルコール性肝障害
E.変形性関節症
穴埋め問題
肥満とはBMI(ア)kg/m²以上を示す状態である。肥満と肥満症は異なる概念である。
肥満症はBMI(イ)kg/m²以上に加えて、減量によりその予防や病態改善が期待できる11の(ウ)のいずれかを伴うものである。
肥満症の治療薬としてGLP-1受容体作動薬である(エ)、GLP-1/GIP受容体作動薬である(オ)が使用されている。
記述問題
肥満症治療薬を使用する上で注意する点を300字以内で記載せよ
解答
選択問題:E
穴埋め問題:ア:25 イ:25 ウ:健康障害 エ:セマグルチド オ:チルゼパチド
記述問題:肥満症治療薬は、まず食事・運動・行動療法を十分に行っても効果不十分な場合にのみ使用する。使用前には内分泌性や薬剤性などの二次性肥満を除外し、原疾患の治療を優先する。インスリンやSU薬、グリニド薬などの糖尿病治療薬との併用では特に低血糖リスクに注意する。急性膵炎、胆道疾患、精神症状の出現に留意し、高齢者では過度の体重減少にも注意する。甲状腺髄様癌の既往のある患者や多発性神経内分泌腫瘍症2型の家族歴のある患者には本剤の安全性は確立していないため留意する事が求められる。(299字)
概要
「肥満症治療薬の安全・適正使用に関するステートメント」は2023年11月に発表されましたが、2025年4月に改訂版が再度発表されました。
肥満症の治療薬としてGLP-1受容体作動薬であるセマグルチド(ウゴービ)、GLP-1/GIP受容体作動薬であるチルゼパチド(ゼップバウンド)は同一成分であるセマグルチド(オゼンピック)、チルゼパチド(マンジャロ)とは独立した臨床試験で肥満症に対する安全と検証プロセスを経た薬剤となります。
「肥満」、「肥満症」の疾患定義と薬剤使用上の定義が異なることを混合しがちなので注意しましょう。
肥満の定義
肥満:BMI ≥ 25 kg/m²。疾患ではなく、単体では薬剤の適応とならない
肥満症の定義
肥満(BMI ≥25 kg/m²)に起因または関連する 健康障害を1つ以上合併する、あるいはその合併が予測され、医学的に減量を必要とする状態
薬剤加療の適応基準
①BMI ≥35 kg/m² で健康障害1つ
②BMI 27–35 kg/m² では健康障害を 2つ以上(高血圧・脂質異常症・2型糖尿病のいずれか+もう1つ)
いずれも肥満症に対する食事運動療法を行なっても十分な効果が得られていない事。
肥満症の診断基準に必要な健康障害11疾患
①耐糖能障害(2型糖尿病、耐糖能異常など)②脂質異常症③高血圧④高尿酸血症・痛風⑤冠動脈疾患⑥脳梗塞・TIA⑦非アルコール性脂肪性肝疾患⑧月経異常・女性不妊⑨閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群⑩運動器疾患(変形性膝関節症:膝関節、股関節、手指関節、変形性脊椎症) 11.肥満関連腎臓病
アルコール性肝障害は含まれません!引っかからないようにしましょう。
使用上の注意点
基本治療(食事・運動・行動療法)を十分に行っても効果不十分な場合に限り薬物治療を検討。
内分泌性・遺伝性・視床下部性・薬剤性などの二次性肥満が疑われる場合は、原因精査・原疾患治療を優先。
単独使用では低血糖リスクは低いが、インスリン・SU薬・グリニドとの併用で低血糖リスク増。
重大な副作用として急性膵炎、胆嚢炎、胆管炎、胆汁うっ滞性黄疸などに注意。
高齢者では過度な体重減少に注意。
高度肥満症患者では精神状態への配慮を行い、メンタルヘルスの変化や自殺念慮のある患者では慎重な対応が必要。
甲状腺髄様癌の既往ある患者や多発性内分泌腫瘍症2型の家族歴がある患者には安全性が確立されておらず、米国では禁忌となっているため注意。
中止によりHbA1cの上昇や肝機能悪化、リフィーディング症候群の可能性があるため中止・再開は十分に注意する。
終わりに
このブログでは今後も記述問題に出題されそうなテーマや学習のコツを紹介していきますので、ぜひ一緒に知識を積み重ねていきましょう。
 | 価格:184円 |
↑ちびたまが好きなおやつ。野菜が入っていると親の罪悪感も減りますね😇
参考文献
肥満症治療薬の安全・適正使用に関するステートメント
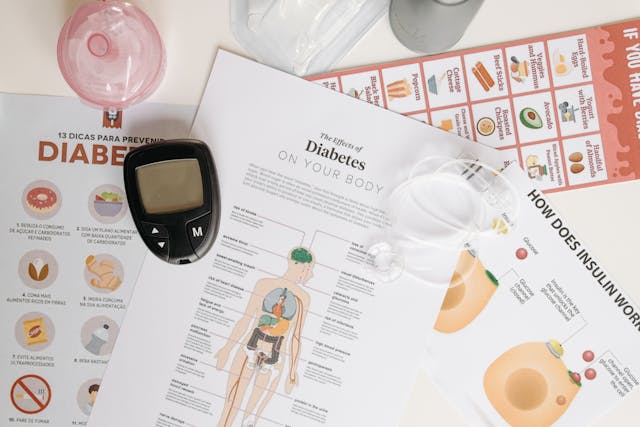


コメント