こんにちは!
しらたまです。
しらたまとは?
30代の糖尿病内科医です。
普段は3歳のちびたま(息子)を育てながら臨床医として働いています。
私は同年度に
第34回糖尿病専門医試験
第2回糖尿病代謝内分泌領域専門医試験
のダブル受験をし、
無事両方とも合格する事ができました。
当時1歳だったちびたまのお世話をしながらの試験勉強は、思い出すだけでも壮絶でした、、、
糖尿病専門医試験の勉強をする中で、一番の難関だったのが、「記述対策」でした。
勉強始めは記述がうまく書けなかったり、想定問題を自分で作るのも難しかったりと壁によくぶつかっていました。
専門医に合格した立場から、今後試験を受けるなら事前に対策しておくなと思う範囲の想定問題と知識のまとめをお伝えします。
※本記事は参考文献を元に個人的に記載したものです。利用時は自己責任で必ず参考文献も確認して下さい。
※誤った記載があった場合には内容確認後に修正するので、ご連絡下さい。
ひとこと
2024年5月に日本糖尿病学会から「インクレチン関連薬の安全な使用に関するRecommendation 第2版」が発表されました。
学会が注意喚起を行なっている内容は試験問題としても出題される可能性があるので、触れておくべきだと思います。
想定問題
インクレチン関連薬について下記の問いに答えよ
1.下記の文章の(ア)〜(オ)の穴埋めをせよ
インクレチンは(ア)(イ)が同定されている。これらは血糖依存的,すなわち血糖が高い時のみインスリン分泌を促進し,血糖降下作用を発揮する.(ア)、(イ)は生体内で(ウ)と呼ばれる蛋白分解酵素により短時間のうちに不活化され,インスリン分泌能を失う.『(ア)受容体作動薬』は,著明な血糖改善効果や減量効果に加え,(エ)や(オ)に対するadditional benefitsが示されている.
2.近年インクチン関連薬の使用が一般化しているが、特に(ア)受容体作動薬を使用するにあたり注意する点を記述せよ(400字)
模範解答
1.(ア)GLP-1(イ)GIP(ウ)DPP4(エ)糖尿病関連腎臓病(オ)心血管疾患
2.GLP-1受容体作動薬を使用時の注意点としては、単独で使用した際には低血糖のリスクは低いものの、インスリン製剤やSU剤、グリニドなどの重症低血糖のリスクが高い薬剤と併用時は十分に注意し、必要ならインスリン製剤、SU剤、グリニドを減量した上でGLP-1受容体作動薬を追加する。インスリンからGLP-1製剤へ切り替え時は内因性インスリンを必ず確認し、特に腎機能低下者では内因性の過大評価に十分注意する。BMI23未満の非肥満患者や75歳以上の後期高齢者への使用の安全性や有効性は十分に評価できておらず、消化器症状の副作用発現割合も高いため注意が必要である。またGLP-1製剤はGLP-1の胆嚢収縮抑制作用から胆石が出来やすくなるため、投与期間が長く投与量も多いほど胆石や胆嚢炎などのリスクが上昇する事が報告されている。使用前や使用中は腹部超音波検査を実施し、胆石の有無の確認や胆道系疾患を疑う症状が出現した際には迅速な対応が必要となる。(398文字(英語と数字は2文字で1字カウント))
内容の要約
1.インクレチン関連薬と重症低血糖が危惧される薬剤の併用
・GLP-1/GIP製剤とインスリン,SU,グリニドとの併用時には低血糖に注意
(DPP4阻害薬+SUほどの低血糖リスクの報告はない)
2.インスリンからGLP-1(/GIP)製剤への切り替え
・腎機能低下例での内因性インスリンの過大評価には注意
3.サルコペニア,フレイルリスクの高い高齢者へのGLP-1(/GIP)製剤の使用
・BMI23以下や75歳以上の後期高齢者では安全性・有効性が十分評価できていない
・BMI25以下の非肥満患者や65歳以上の高齢者は消化器症状が出やすい
4.インクレチン関連薬と水疱性類天疱瘡
・現状では選択性の低いDPP4阻害薬で多い
・GLP-1(/GIP)製剤では問題視されていない
5.インクレチン関連薬と膵疾患
・DPP4阻害薬の使用で頻度は低いものの、急性膵炎の有意なリスク上昇が認められたが、GLP-1(/GIP)製剤では急性膵炎の上昇は認められていない
・膵癌のリスクは DPP4阻害薬,GLP-1(/GIP)製剤いずれも上昇させない
・急性膵炎リスク→アルコール多飲、胆石、肥満
・T2DMは膵癌のリスク高いので元々注意
6.インクレチンと胆道系疾患
・DPP-4阻害薬の使用期間が長いほど胆嚢炎のリスク上昇
・GLP-1製剤も使用期間が長く、投与量が多いほど胆嚢炎のリスク上昇(GLP-1には胆嚢収縮抑制作用があり、胆石ができやすくなる)
・GLP-1/GIP製剤は現状だと胆道系疾患との関連の報告はないが、注意が必要
・DPP4阻害薬、GLP-1製剤の使用中に胆管癌のリスク上昇の指摘があるものの、ランダム化比較試験のメタ解析からは明らかなリスク上昇は認めてられていない
7.インクレチン関連薬とRS3PE症候群
・DPP4阻害薬の使用に伴うRS3PE症候群の発症報告がある
・RS3PE症候群:対称性滑膜炎による末梢関節炎、両側手背・足背の圧痕を残す浮腫、手指屈筋腱の炎症による疼痛がある場合に疑う
・RS3PE症候群を疑った場合はDPP4阻害薬中止の上で膠原病内科へコンサルトを行う。治療には副腎皮質ステロイドの加療が必要となるので、血糖コントロールに注意する
・現在まで、GLP-1(/GIP)製剤でのRS3PE症候群は問題視されていない
終わりに
一度参考文献に目を通してから、まとめとして要約部分を利用してもらうのがいいかと思います。
これからも定期的に記述の予想問題を作成したいと思っています。
 | 価格:2560円 |
オイコスのヨーグルト高いけど美味しい。
参考文献
・インクレチン関連薬の安全な使用に関するRecommendation 第2版 日本糖尿病学会
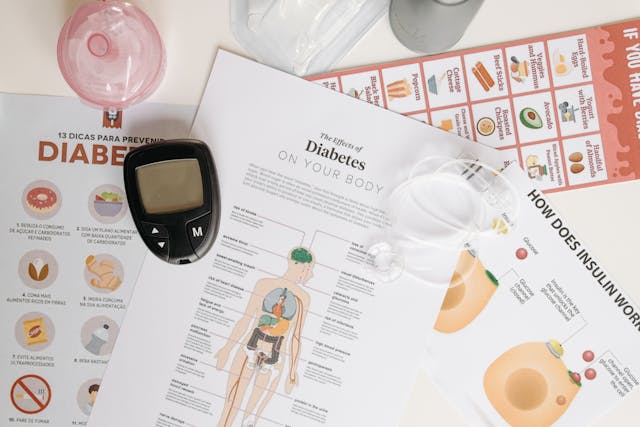


コメント